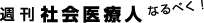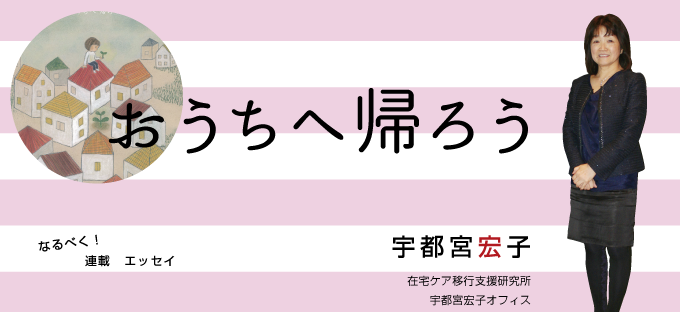入院はあくまでも通過点、病院は生活の場ではない、
人生の幕引きの場にはならない
2000年、在宅医療の現場で、介護保険の幕開けを迎えた私は、
在宅療養者に専門相談員(ケアマネジャー)が担当になり、
望む暮らしを支え、できれば生活の場で人生の幕引きが迎えられる事が当たり前になると、
大きな期待を抱いていた。
訪問看護ステーションを複数持つ医療機関で、
訪問看護統括管理の立場になり、
病院で、どのように退院が決まり、
本人不在の場面で、在宅へ戻る事を諦め、
転院先や施設を探す状況を見て、
病院の中で「生活の場へ患者を帰す専門的な看護師の関わり」が必要だと考え、
大好きな訪問看護から大学病院へ戻った。
勤務していた法人はMSWが退院調整をする事で問題はないと、
看護師による退院調整のシステムについては必要性を認められず、
退職をして出身大学附属病院へ着任した。
病院に勤める医師や看護師、在宅経験のないMSWには、
訪問看護や在宅医とケアのサービスをどう組み立てる事で、
在宅療養が可能かをイメージする事が難しいため、
「家は無理よね」と、在宅へ帰る事を諦めてしまう。
訪問看護の経験者が「在宅医療コーディネーター」をすることで、
多くの患者が自宅へ帰れると考えていた。
着任した翌日から、病棟からの依頼箋をもって、
コーディネーターとして回り始めた。
依頼箋には、医師と看護師の記載する欄があった。
医師の欄には、「○○癌、ターミナル期にある、疼痛コントロール中、家族は高齢な妻、転院先検索依頼」と書かれている。
看護師からは「寝たきり状態、全介助」といった今の状況を電子カルテ用語で、淡々と伝える内容の依頼文。
まったく患者の様子がイメージできない、
電子カルテに記録されているのは医師の指示と実施した記録、
患者の言葉が、表情が見えない記録。
「患者さんは今の自分をどう思っているんだろう、
ずっと外来で抗がん剤治療を受け、病気と闘ってきたのに、
今は患者の思いが見えないまま、当事者不在の中で、方向性を決めようとしている、
患者さんの人生の大事なところやん、誰のものでもない患者の人生やん」と、
一人怒りモードの私は、病棟看護師や医師の「何? この人?」という反応を浴びながら、
家族や患者のそばにいって、思いを聴く場面つくりから、私の活動は始まった。

訪問看護時代の著者
在宅では、真ん中に患者がいる、
「あなたに起きている事、病気・老いにより今までとはどう変わっていくのか、
でもできる事、症状を軽減し、安楽に暮らす方法をみんなで考えていこう」と
医師やヘルパー、ディサービスの相談員等々、患者を取り巻く人たちと考える、
そこには「患者がどう生きたいか」を支えるチームの姿があった。
病院での私は、不安でいっぱいだった。
退院を拒否する妻や子供さんたちと
「お父さんにとってのいい時間を一緒に創りませんか?」と伝えた時の、
家族の優しい涙を見たとき、
「あ~、大丈夫、家族の思いは、患者の願いをかなえる事」と、
話し合いの入り口が、扉が開く。
院内で成果も見え始めた頃、
肺癌で、脊椎転移、下肢麻痺が出て、放射線治療等実施されたが、
改善せず、退院支援の依頼がでた。
彼は、50代の歯科医、
「こんな事になる可能性があるのなら、言ってほしかった。
今更、どう生きたいか、なんて言われて何ができるんだ」
と怒りをぶつけてきた。
脊椎転移については、当然聞いているが、
自分がどう変わるかも知れないという予測はできないし、
想像する事はつらい事。
退院支援は、病院から退院する出口の問題だけではない。
患者が病気と向き合った時からの
「どう生きるかを支える」視点を持って仕組みを作る必要があると考え、
3段階プロセスを基にシステム構築を始めた。
※掲載内容は連載当時(2013年9月)の内容です。