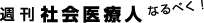連載第3回の今回は、沖縄の誇る銘酒、泡盛についてです。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私は沖縄県知事認定の泡盛マイスター。
もともと、ソムリエ、ワイン・エキスパートなどの資格を持っていた私ですが、
沖縄に移住し、沖縄の独特の気候のなかで毎日過ごしているうち、
仕事の後の一杯の泡盛がとても心地よいことに気付きました。
そこで、せっかく沖縄にいるのだから、泡盛も究めてみようと、
泡盛マイスターにチャレンジしたわけです。
泡盛マイスターの試験は、筆記、サービス実技、テイスティングの3科目。
泡盛のテイスティングは、原料がみな同じタイ米と黒麹、製造工程も概ね共通、
外観もほとんどのものが無色透明…ということで、
ワインのテイスティングに比べてもはるかに難しいんです。
まったく自信はありませんでしたが、運良く1回で合格することができました。
泡盛がほかのお酒と比べても引けを取らない点は、
黒麹を用いることで生まれる独特の深いコクと、熟成によって増していく風味です。
黒麹のすばらしさは、最近の芋焼酎が黒麹を使用した製品を発売していることでもおわかりですね。
『黒○○』という名前の付いた焼酎は、
『沖縄の黒麹』を用いた製品と思っていただいて差し支えありません!
有名な銘柄がいくつも思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか?
沖縄の黒麹、恐るべし!!
そんな黒麹、泡盛造りには、琉球王朝時代から使用されていて、
その正式学名は、な、なんと、アスペルギルス・アワモリなんですョ。
コミック『もやしもん』にも登場しています!!
どうですか、泡盛の深さ、その片鱗がわかっていただけたでしょうか?
泡盛にとって、もう一つの大事な要素、『熟成』は、黒麹以上に深い神秘に満ちています。
泡盛の熟成は、ほかのお酒のように「まろやかになる」程度のものではないんです!
原料のタイ米に含まれるフェルラ酸は、4‐VGという物質を経て、
熟成によって、バニラの香りのもとであるバニリンに変化するんです。
バニラの香りは、実は、世界中のあらゆる民族が好む香りなんだそうです。
ロングセラーの栄養剤がバニラ風味なのは、そのためだとか。
数年〜数十年熟成を重ねた泡盛は、さまざまな化学変化によって、
バニラのほか、キャラメル、梅の花、トロピカルフルーツといった、
原酒からは想像も付かない華やかな香りを放ちます。
ウイスキー派の方は、ウイスキーでも、いい樽を使ったものは、
バニラや、バタースカッチ、焦がしたカラメル、スモークなどのさまざまな香りがある…、
とおっしゃるかもしれません。
自分は、ウイスキーも嫌いじゃないので、その辺はまったく賛成です。
しかし、それでもなお、泡盛が凄いのは、
バニラなどの香りが、原料由来物質の化学変化によって生まれているということです。
ウイスキーやブランデーなどの多くは、数回の蒸留によって原酒が作られるため、
原酒の風味はとてもシンプルなものになってしまいます。
その原酒を樽で熟成することによって、
樽の材質のオークなどからバニラの香りが移行するわけです。
すなわち、後付けなんです。
泡盛と、ほかの蒸留酒との違い、わかっていただけましたか?

泡盛は、ステンレスタンクや瓶のなかでも熟成しますが、
もっとも熟成がよく進むのは、昔ながらの甕(かめ)による貯蔵法だといわれています。
琉球王朝時代から、泡盛では、「仕次ぎ」という方法が行われていました。
年代の違う泡盛の甕をいくつか用意し、一番古い甕から古酒を汲み取ったら、
その減った分をそれより若い二番甕から注ぎたし、二番甕には三番甕から注ぎたす…、
といった方法です。
スペインのシェリーとも似ていますね。
このような方法で、戦前は、百年どころか、
二百年近く熟成した泡盛も存在したといわれています。
トロピカルテクノセンターの塚原正俊氏は、最近、この「仕次ぎ」を行うことによって、
4‐VGからバニリンへの変化が促進され、バニリンの濃度がさらに上昇することを発見しました。
琉球王朝時代から受け継がれてきた技術の真価を、最新の科学技術が解き明かしたのです。
分析装置などもないのに、黒麹の使用や、熟成の技術などを確立した琉球王朝の人々。
そのすばらしい感性と、努力には、頭が下がる思いですね。
現時点で科学的なエビデンスではなくても、
私たちが日頃感じていること、日々行っていることのなかには、
まだまだその真価が証明されていないことがたくさんあるのかもしれません。
私たちも、琉球王朝の人々を見習って、感性を研ぎ澄まし、
毎日の臨床に専念していきたいですね。
次回は、『死と音楽』などについて書いてみたいと思います。
※掲載内容は連載当時(2011年2月)の内容です。