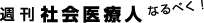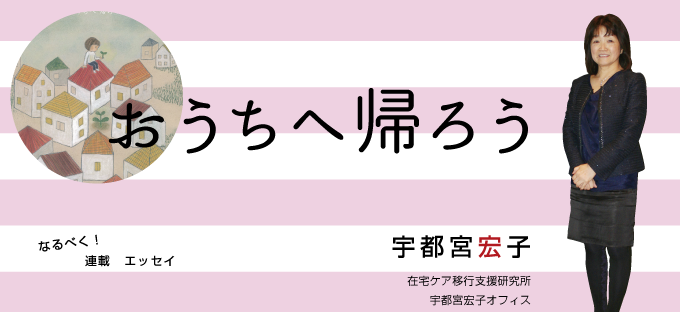入院した患者さんが、どんな医療を受けて(入院目的・治療方針)、
どういう状態像になるかを早期に看護チームで共有する。
入院前の生活ぶり(ADL、IADL)と比べて変わる事はないかを考え、
患者さんが望む暮らしの場へ帰る事が可能になる備えをする。
病棟看護師と週に1回、集まりカンファレンスを始めた。
退院支援カンファレンスだ。
規模の大きい病院になると病棟の特徴がある。
座学の全体研修では特徴を踏まえた教育ができない。
オンゴーイングの患者さんを通して「気づき、思考し、行動するプロセス」を学ぶのは、
現場のカンファレンスが効果的だと考え、熱心に退院支援に取り組んでいる部署で始めた。
意識の高い部署は対象者が多く発生する病棟であること。
それに私一人がスーパーサイヤ人になって動いても現場は変わらない。
病棟看護師の力を引出し、自立して退院支援ができるようにサポートする事が目的だ。
診療科、主に診る病気によって退院支援が必要な患者の状態像が違い、
マネジメントするプロセスにも特徴がある。
手順、業務マニュアルといった質を保障する標準化は、病院や介護現場でも作成され、
手順に沿った看護、ケアを提供する事を目指す。
しかし、退院支援、退院調整のプロセスは、情報からどう考えるか、
どう動くかといったマネジメントのプロセスになる。
脳外科病棟では、毎週病棟医長が日勤看護師に対して、
手術予定患者の紹介と術後管理等をプレゼンする時間に、私が参加して開始した。
既存のカンファで「どこへ帰るのかな、そのために準備が必要だね」を
ちょっと意識する働きかけをする。
若い膠芽腫の男性、治療方針と部位の問題から、腫瘍をすべて除去できない事が説明された。
病棟師長達は術後ICU経由しないで病棟管理になるため、
人員体制の帰室時間の確認などをしていた。
私は外来カルテの最初の記録を読む。
会社で仕事のミス、道に迷うといったことが続き、
「認知症ではないか」と会社の人に言われて家族と受診した経緯が書かれていた。
まだ幼い子供がいて妻は専業主婦だ。
「全部除去できないという事は高次脳機能障害は残りますか?」と医師に確認した。
「会社復帰は厳しいのかな、機能障害はなくても生活動作は自立できるのかな」といった、
“治療後の状態像”についての予想を問う。
医師にとっては嫌な質問。
今から頑張って治療しようとしているんだもんね。
「経過見ないとわからないけど職場復帰は厳しいかな」
「そうすると、経済的な問題が大きいかもね。奥さんが不安を抱えているかもしれないし、
今後の生活の相談という事で思いを聴いていく必要があるね。
術後の状況みて、OT(作業療法士)に高次脳機能評価を依頼して、
MSWと一緒に奥さんとの面談を設定しましょう」と支援を皆で考え、計画する。
患者や家族が抱えている不安や思いに寄り添いながら、
治療やリハビリの経過を見て、必要な支援、調整をしていく。
皆に質問する内容(支援に必要な情報)、治療経過に合わせてマネジメントする事、
在宅への調整も含め、病棟、患者状態像によって一定のパターンがある事に気づいた。
在宅療養への移行を支援するためのプロセスを見える化、可視化する事ができる。
2011年に京都府看護協会で『在宅療養移行支援ガイド~医療依存度の高い患者を中心に~』という冊子を作成した。
京都府下の退院調整看護師が集まり、先駆者の経験値を可視化する作業だ。
訪問看護師や医師会とも相談しながら、
京都での在宅療養移行の質を保障するためのテキスト、ガイドブックとして完成させた。
2013年、東京都では「退院支援マニュアル~病院から住み慣れた地域へ、安心した生活が送れるために~」を部会長として関わり、
東京で在宅や退院支援に取り組む先駆者たちと共に作成した。
実践者の経験、成功体験を地域全体の財産として活かすために、
関係者が集まり、現状を語り、どうありたいか、目指す姿を共有し創造していく。
東京都での部会では「私が受けたい支援、当事者目線で、受けたい支援、調整」を
まず部会全体で共有する事に集中した。
「退院支援・退院調整フロー図」は可視化したもの。
その中で必要な知識やツールを丁寧に作る作業へと発展していった。
ぜひ、東京都のみならず多くの病院で、地域協働で活用してほしい。
マニュアルは東京都保険福祉局のホームページからダウンロードが可能。
成果物を作る事ももちろん大事だけど、
作るまでの過程とその後どう現場で活かすかが何より重要だ。
今年は実践、評価へと事業は続く。
その先に患者さんの笑顔があると信じて頑張って欲しい。
※掲載内容は連載当時(2014年8月)の内容です。