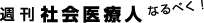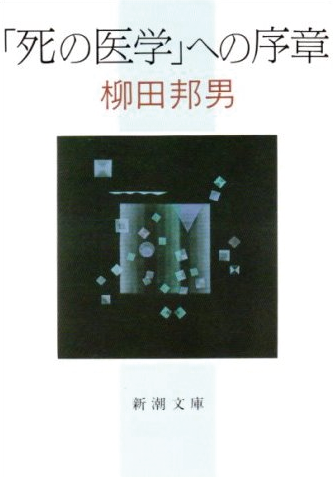
九十七歳になる母方の祖母が誤嚥性肺炎で入院しました。
短歌の会を主宰するなど矍鑠(かくしゃく)としていたのですが,
さすがに年齢なりに認知症気味となり足腰も弱りました。
三年前に転倒して大腿骨近位部骨折の手術で入院して以来,
この齢で感心にも生まれて2回目の入院です。
三年前に家内と御見舞いに行った際には,すでに認知症が始まっており,
祖母は私の顔を見るなり「英治ちゃん,大きなったなあ」と言いました。
家内には「あんたは,えらい別嬪さんやなあ」と言ったので,
家内は「ちっとも,ぼけてはらへんやん,しっかりしてはるわあ」と,
エビデンスレベルがきわめて低いと考えられる会話を交わしておりました。
さすがに今回はだめかもしれないと母が言うので,
一応身内の医師代表(私の父すなわち母の夫も医師なのですが,母いわくロートル医師は信用できないとのことで)として,
御見舞いがてらに病状を診に行きました。
祖母は私を見て笑ったようには見えましたが,
話すことはできず意思疎通は不可能でした。
ただ意識は清明でバイタルは安定しており『まだ大丈夫そう』という具合でした。
呼吸も楽そうで発熱も無かったので,肺炎も抗菌薬が効いて快方に向かっているようでした。
伯父から今後の見通しを訊かれました。
祖母のようなケースは,昔であれば肺炎に罹り身体が弱って食べられなくなった時点で自然に死を迎えたでしょうが,
昭和50年代以降は在宅で高齢者が死を迎えることが病院死の割合より少なくなりました。
肺炎が治り食事が再開できて,自宅なり施設に帰れれば良いのですが,
とくに超高齢者の場合は弱ってしまって,経口摂取が再開できないケースも多いのです。
食物を認識できない,咀嚼や嚥下ができない場合も消化吸収機能はありますので,
経鼻経管栄養や経胃瘻栄養にすれば生命を維持することは可能です。
たいてい本人は意思表示ができませんので,
医師から御家族に経管栄養などの強制栄養を行うかどうかを伺うことになります。
高福祉といわれる北欧諸国では超高齢者が衰弱して口から食事が取れなくなった場合は,
それが寿命と受け入れて強制栄養は行わないそうです。
日本では老衰であっても自宅で死を看取った経験の無い家族が増えたため,
超高齢者の死も自然経過のままに受け入れることができなくなっているのかもしれません。
昨年は高齢者の死亡を届けずに年金を詐欺していた不埒な子孫たちが多くいることが明らかになりましたが,
日本には高齢者の年金をあてにしている下品な人が少なからずいることも事実です。
それはともかく,人は年を取ればいずれは死ぬという教育が十分にできていないことも問題でしょう。
我々医師は診断と治療の教育は十分に受けますが,ほとんどは延命のための教育です。
近年になってQOLや緩和ケアや尊厳死ということも大事であることがやっと教えられるようになってきました。
ノンフィクション作家の柳田邦男氏には「がん回廊の朝」などの医療や死の臨床に関する著作も多く,
「死の医学への序章」は,がんで亡くなられた精神科医西川喜作先生の闘病記の形式で,
医学生への「より良き死へのサポートの大切さ」の教育の必要性を述べています。
医師の世界では「五年生存率が向上した」ということは評価されても,
「生存期間の延長は無かったがQOLが向上した」とか
「安らかな死を迎えられた患者が多かった」ということは評価されないということも問題でしょう。
人は生きている時間の長短よりも,
生きている時の生活の質が大切であることを再認識させられます。
ところで,祖母の件につきましては,
結局頼りない医師親族代表の私の見立てから
「肺炎が治れば,また口から食べられるように体力が回復するかもしれない。
でも老衰での誤嚥なら,肺炎が治っても食べられない可能性もある。
そうなると主治医からは強制栄養をするかどうかを相談して決めて下さいと問うてくると思う」と伯父に説明しました。
伯父は「母がしっかりしていたら,『そこまでせんでよろし』と言うだろう。
肺炎が治っても口から食べられなければ,無理にしんどい目はさせたくないから,
母の回復力にまかせよう」と言い,私も「僕もそう思います」と答えました。
そして,祖母はなんと嚥下訓練を経て無事に経口摂取を再開して,
お粥も美味しそうに食べるようになって退院したのでした。
高等女学校時代に駅伝の選手であった体力はだてではありませんでした。
※掲載内容は連載当時(2011年2月)の内容です。