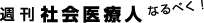卒業して医師になって3か月救急、
その後3か月外科を回るローテーションです。
その初めの3か月で、歌って踊れる産婦人科医を目指していた私が、
消化器外科医に変わったのでした。
ままならないものです。
今の外科医は乳腺外科も含めて胃や大腸、肝臓など臓器別に分かれていますが、
25年前では外科医はすべての手術をできるのが当然です。
研究は臓器別に行うこともありますが、
臨床はなんでも見られると言うのがそのころの外科医でした。
外科の講師クラスでも大腸がんの手術をやった翌日に、
膵臓の手術を行うと言うのが当然の時代でした。
今では考えられないでしょうね。
抗がん剤も今のようにいろいろな種類があるわけではないので、
とにかく手術でうまく大きく取ることが一番の時代で、
外科医の腕の見せ所だったかもしれません。
そのようななかで、
徐々に外科医も臓器を持つ必要があるという認識が少しずつ出てきました。
私を外科に誘ったM講師は防衛医大に来て大腸を自分のライフワークと決められました。
そして初めて大腸グループをつくったわけです。
と言っても、M講師、H先輩そして私の3人だけです。
だから学会の準備も3人、学会に出かけるのも3人なわけです。
そのころは学会出張には製薬メーカーがついて来てくれました。
切符の手配や地元の美味しい店の予約なども、
すべて製薬メーカーがやってくれるわけです。
今では考えられないバブリーな時代でした。
忙しい大学から離れて、仲の良い3人で大名旅行ですから楽しいものです。
そして学会ではいろいろな取り組みを勉強して帰り、
臨床に役立てようと必死で勉強しました。
今みたいにインターネットもなく。手術のビデオもないわけですから、
その場で手術の大家の話を聞いて頭に入れなければいけません。
これも今とは違うことですね。
さて手術の勉強もこんな感じでしたが、検査も今とは違うものでした。
特に内視鏡検査は、今みたいに大きな画面をみんなで見ながらではなく、
術者一人が手元でのぞきながらシャッターを押して写真を撮るのです。
もちろん管の太さも今の何倍もあって、患者さんは苦しさのあまり、
自分で引っこ抜いたり、怒鳴り合いながらの検査でした。
特に大腸検査は苦しさの極みでした。
術者しか見えませんから、
助手が術者の「進めろ」、「少し引け」とかという指示で進めていくわけです。
でも助手は見えないわけですから何も面白くなく、
怒られるだけで助手にとっても苦痛でした。
一番つらいのはもちろん患者さんでした。
1時間以上検査されてお腹は空気でパンパンになり、
腸はねじれて痛みは半端なくて大騒ぎでした。
患者さんの口からは、「誰か助けて~~」
「けんすけ~お母さんはお医者さんに殺される~~」とかの大声が発せられました。
術者は「動かないでください、腸が破れますよ」と初めはやさしく、
そのうち「危ないだろ、動くな」
「これぐらい、がまんできるだろ、子供じゃないんだから」
「もういいよ、我慢できないあんたが悪いんだからな、がんがあっても俺は知らないからな」
などとパワハラまがいの脅しも出てました。
こういう状況ですから、次の順番を廊下で待っていた患者さんが、
恐ろしくなって検査をやめて帰ることもたびたびありました。
恐ろしい時代ですよね。
大腸カメラだけはやりたくないと私自身、思ったものでした。
ところが今、私は毎日4件の胃カメラ、1件の大腸カメラを行っています。
胃カメラは経鼻内視鏡で楽ですし、
大腸カメラも10分以上行うことはほとんどありません。
自分でとっても上手になったな~~と思いますが、
現実は私の腕が上がったわけではなく、ほとんどは機器の進歩によるものですね。
先日うちに来られた患者さん、大きな病院で大腸カメラを2時間もやられて、
苦しくて死にそうだったと言われていました。
今の時代もそのような医者がいるんだなと何故か妙に感心しました。
※掲載内容は連載当時(2013年9月)の内容です。