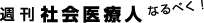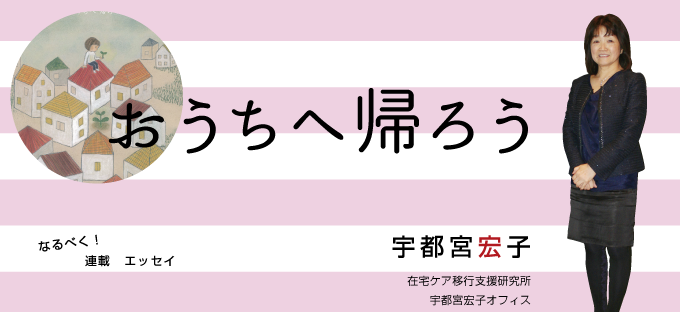「MSWと退院調整看護師の役割の違いは何ですか?」とよく聞かれる。
医療の専門家、福祉の専門家である事を基本に何点かあるけれど、
一番に挙げたいのは「病院の看護師や医師の意識を変える、文化を創る事」だと思う。
2008年、診療報酬上で「退院調整への評価」が初めて認められた。
急性期病院は「退院調整部門」を設置し、看護師と社会福祉士の両職種が病棟の医師や看護師とチームを組み、退院支援に取り組む仕組み作りが加速した。
急性期病院には「退院調整部門が配置され、看護師が配置されている」。
いちおう…。
「な~んちゃって退院調整看護師」と、私が講義でよく皮肉を言って嫌がられているが、
前年度末の3月まで病棟や外来で働いていた看護師が、
新年度の4月から突然、地域連携室や在宅支援室に異動を命じられ、
「今日から退院調整看護師です」と動かなくてはいけないのだ。
「宇都宮さん、病棟の看護師はちっとも患者さんの思いを聞いていないんです。
入院前の暮らしのことや病気のことなど、どう受け止めているのか、
それを聞いていない、把握していないんです。」
と怒りモード全開です。
「そうだね、じゃ、あなたは病棟にいたとき聞いてた?」
「…、聞いてなかったです」。
なぜ、退院調整看護師になったらそのことに気づいたの?
退院支援に関わると患者さんを時間軸で捉えていく。
入院前の暮らしから入院中、そしてその後どんな生活になっていくのか、
どこへ戻っていくのかを、その人の人生の一部として考え始める。
何より大きなことは、
“患者さん、当事者不在”では何も決まらないという当たり前の事実に気づくことだ。
救命・治療を最優先に情報を取り、安全な医療を提供をする事が中心になっている急性期の現場では、その時期が終了した後の患者のことはイメージもわかない。
ましてや、退院困難になる可能性のある患者は急性期病院の医療者にとって“困った患者”。
嫌いな言葉だけど“パスに乗らない、バリアンス”になる患者さん。
本人の思いに一歩近づいて、一緒に考える退院支援になっていない。
当事者不在。
でも、「転院した○○さん、どうしたかな? リハビリして家帰れたのかな?」
「家に帰りたいって何度も泣いていたがん患者さん。
ホスピスへ移っていったけどこれで良かったのかな」
と、その後の患者さんの人生に思いを馳せる瞬間が、看護師にはあると思う。
多忙な中、確認する事も出来ないけど、
走馬灯のように患者の顔・声が浮かんでいると思いたい。

もう8年位前だが、退院支援の講演終了後、看護師になって2年目という若い看護師がこんな話をしてくれた。
病院でせん妄状態になった男性患者の手足を抑制し、車いすでは抑制ベルトをつけた。
それでも興奮して、医療提供もままならず自宅退院となった。
彼女は「どうしているだろう」と気になって、そっとお家へ行ったそうだ。
奥さんに見つかり「今、主人は出かけているけどもうすぐ戻ってくるから」と、家で待たせてもらった。
「デイサービスにでも行ってるのかな」と思った彼女の目に入ってきたのは、
満面の笑みで自転車に乗って帰ってくる患者さんだった。
「近くまで釣りに行ってたんや」と言いながら…。
「看護って何だろうって、見えなくなって受講しました」という言葉に、
私は感動と同時に、若い看護師達に看護の本来の役割を胸張って伝えていない現状を
何とかしなくてはいけないと感じた。
転倒から守るために管理・抑制するだけでなく、入院環境で不安になることを当たり前の姿と理解し、「大丈夫」とそばにいる、支える看護。
「先生の話、つらかったですね。一緒にこれからのこと考えていきましょうね」。
くやしさ、怒り、ぶつけられる事もあるけど、そばにいる、一緒にいる、伴走する看護。
退院支援のプロセスの2つの柱は、
「意思決定支援(自己決定を支える)」「自立(自律)支援」だと私は考えている。
何も新しいことだとは思わない、看護そのものである。
治療の限界がみえている、障害が残る、医療処置や管理が今後も必要。
それでも、にもかかわらず、あなたらしく生きる。
一緒に考えて、構築していくこと、人生の再構築を支援すること。
退院支援に取り組むことが、「生活者」である患者に寄り添う看護を取り戻していく。
※掲載内容は連載当時(2014年2月)の内容です。